教授あいさつ
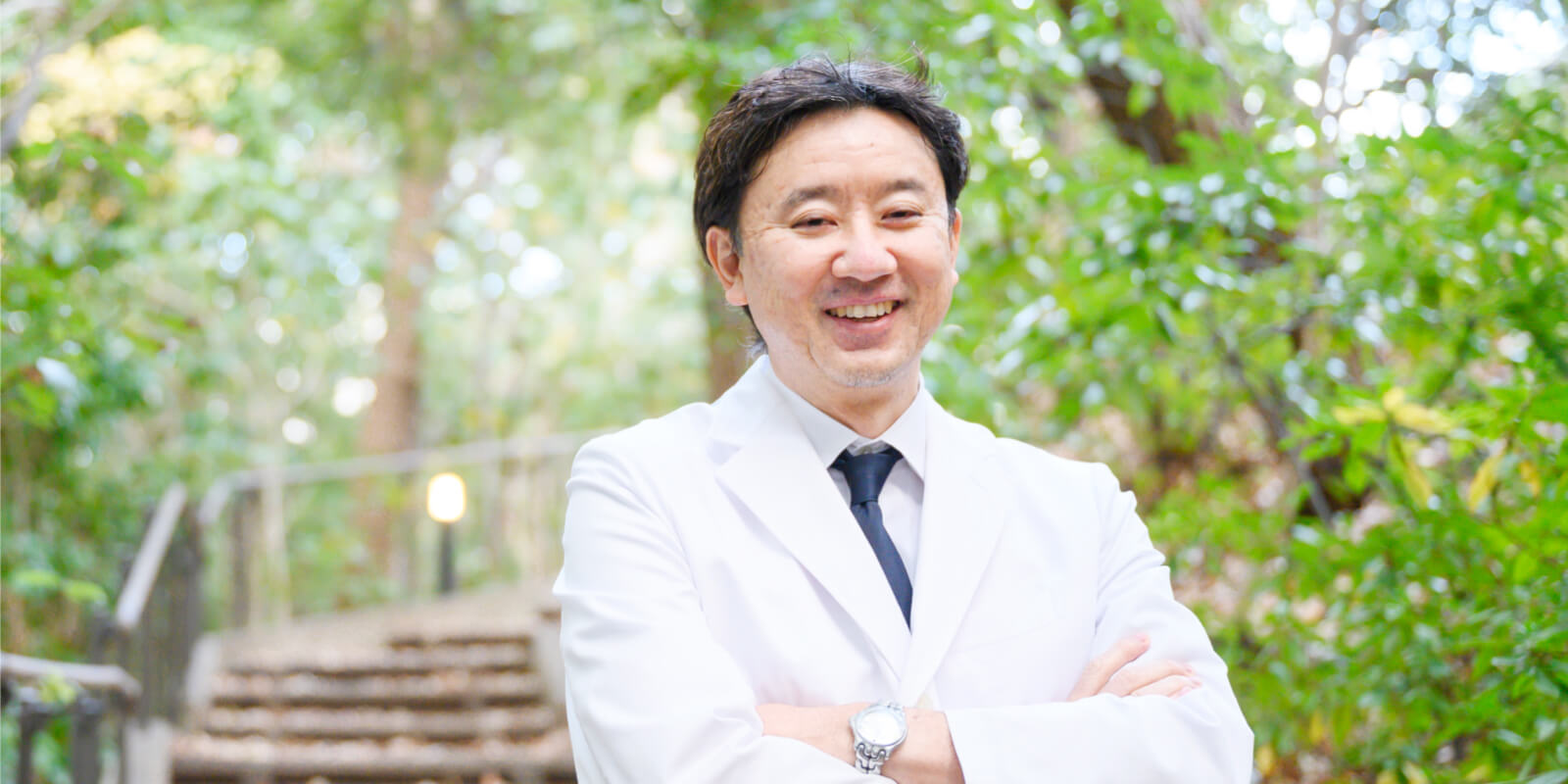
肝胆膵内科は専門分野が多く、興味ある選択肢が必ず見つかります。
実力を試したい方、高めたい方、全国どこからでも見学に来てください。
教授 伊藤 清顕
我々の肝胆膵内科では、肝臓グループと胆膵グループの2つのグループで分担して患者さんの診療、学生や研修医、専攻医の教育、そして基礎および臨床研究を行っています。私は、主に肝臓分野の診療と教育、研究に携わっていますが、胆膵分野にも興味があり、両方の症例カンファレンスや研究に関わっています。そもそも、肝臓と胆道(胆管および胆のう)、膵臓は解剖学的、また消化や吸収という機能的な面からもそれぞれが密接に関連しています。ただ、その疾患の特徴は大きく異なっており、肝臓の疾患は慢性肝炎や肝硬変など比較的じっくりと時間をかけて病態や診断を考えて治療方針を立てる症例が多いのに対して、胆膵疾患では急性胆のう炎や急性胆管炎、急性膵炎など急性疾患の比率が高く、すぐに処置や治療が必要となるなど行動力が必要となります。こうした違いも考慮して、当肝胆膵内科では皆さんの性格や希望に合わせて専門の診療分野を決めていただくことができます。肝胆膵の分野には多くの専門分野があり、皆さんの興味を満足させる分野が必ず見つかるでしょう。ウイルス性肝炎をはじめとした感染症分野、脂肪肝や肥満など代謝や栄養に関する分野、自己免疫性肝炎や自己免疫性膵炎などの免疫系分野、腹部エコーを極めるのも良いですし、CTやMRIなどの画像診断を得意にするのも良いと思います。また、肝胆膵内科が扱う悪性腫瘍は膵臓癌や胆道癌、肝臓癌など現在最も治りにくい悪性腫瘍であると考えられています。このような難治性悪性腫瘍に対して、当科では最新の内視鏡検査や内視鏡治療、局所療法や分子標的薬などを駆使して全力で立ち向かっていますが、それでも治療成績は満足できるものではありません。こうした現状を打破するために難治性悪性腫瘍に対して一緒に立ち向かってくれる方も募集しています。
研究に関して話をすると、現在、私は国から研究費をもらってB型肝炎に対する新しい薬の開発に携わっています。これは、胆汁酸という肝臓で産生される物質を創薬のターゲットにしていて、B型肝炎に対してだけでなく、脂肪肝や糖尿病の新しい薬になる可能性があります。新しい薬の開発は、目の前の患者さんだけでなく多くの患者さんを救うことができ、たいへんやりがいがあります。当科では基礎研究や臨床研究を非常に活発に行っており、皆さんには最新の研究方法や技術、知識を習得してもらい一緒に研究することが可能です。希望があればナショナルセンターなどへの国内留学や海外留学も可能です。このように当肝胆膵内科では診療や研究においてやることが山ほどあり、皆さんの実力を精一杯発揮することができます。自分の実力を試したい方、どんどん実力を高めたい方、最新の研究や技術に興味のある方は、是非一度我々の行っている診療、教育、研究を見ていただき、色々なお話をさせていただきたいと思います。当大学からはもちろん全国どこからでも構いませんので、是非一度見学に来てください。
見学希望者や質問等がある方はお問い合わせフォームから御連絡いただけますと幸いです。何なりとお尋ねください。よろしくお願いします。

